就職活動の後ろ倒し以来、急速に広まった”インターンシップ”。
会社見学型の1dayインターンが大多数を占める中、長期インターンの役割は何でしょうか。
地方ではUIJターンの促進として行われる場合もあります。
今回は、あまり知られていない効果について、書きます。
長期インターンでよくある誤解
「長期インターンをすることで、採用ができなかった会社に人が来た!」
巷には、こんな都市伝説が流れていたりしますが、
残念ながら高確率で採用できるようなデータは見たことがありません。
もちろん、長期インターンする人は、会社、業界・職種に興味があるのは確かでしょう。
ただ、長期でインターンさせるコストと採用率を考えれば、
説明会や1dayを使った「数の勝負」の方が効果的だと思います。
長期インターンでは、長期間一緒に働いて、
お互いに相性を見ることで、ミスマッチを防ぐ効果はあります。
ただし、インターン生にバイトの内容をやらせている場合には、
悪印象になることがあるので注意してください。
長期実践型インターンシップとは
長期の実践型インターンはどうでしょう。
まずは、短期のインターンとの比較です。
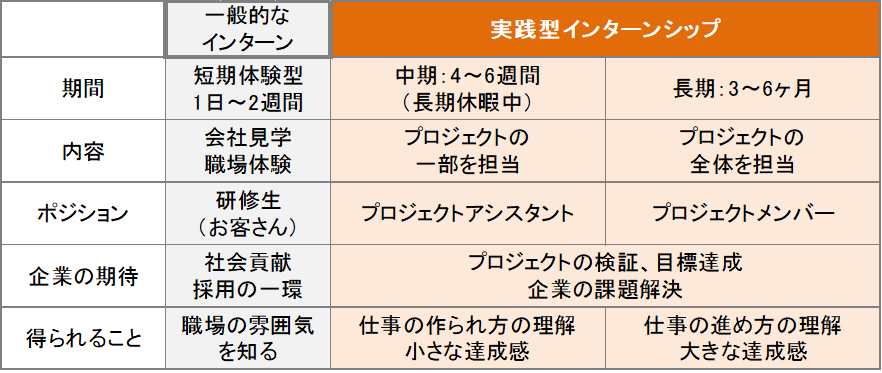 (※記事内では、便宜的に中期と長期を合わせて、長期と記載しています。)
(※記事内では、便宜的に中期と長期を合わせて、長期と記載しています。)
「期間が1ヶ月以上の長期」「企業内のプロジェクトに取り組む」という2つが大きな特徴です。
見学・体験という「お客様」より、「期間限定の正社員」というイメージですね。
プロジェクトは、インターン生のために用意するのではなく、
企業が本気でやりたいと思うプロジェクトです。
企業も学生も本気で取り組みながら、両者が学び合う関係を築いていきます。
また、金銭的な報酬は、あえてバイトより低く設定しています。(理由は後述)
それでは、長期インターンは、なぜ採用につながるのでしょうか。
まず前提として、「インターン生が入社する」とは考えていません。
「インターンを通して、入社したい会社へ変わる」という考えです。
どう変わるのかを詳しくみていきます。
永続性や将来性を高める
企業が本気でやりたいプロジェクト。
その切り出し方を、4象限のマトリクスで説明します。
「緊急度」と「重要度」の2つの軸で切ります。
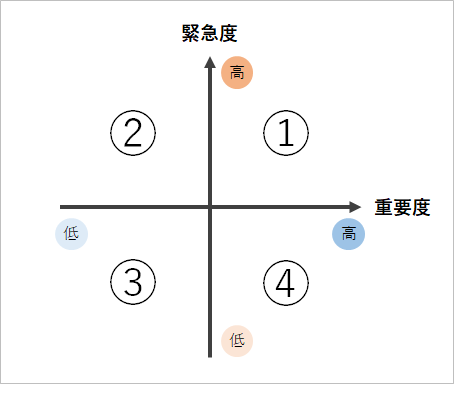
①は、現在の主力事業など。
②は、バックオフィスなどの非生産部門です。
どちらもやってないとマズい。
③は、やる必要がありません。
④は、やっておいた方がいいのですが、後回しになりがちです。
特に人手不足だと、ここに人を割けません。
しかし、変化の激しい社会で、④をしておかないのはリスクがあります。
既存事業は衰退していきますから、新しい事業をつくりながら、生き残っていかないとなりません。
潜在ニーズの掘り起こしや、現場の課題解決など、将来への投資は欠かせない。
長期インターンでは、人手付きで④に取り組むことができるのです。
まず1つ目は、会社の永続性や将来性を高めることに繋がる点です。
非金銭的な報酬を高める
人が働きたいと思うモチベーションを、また4象限で考えます。
「金銭」と「非金銭」の2軸で切ります。
「非金銭」は、やりがいだったり、楽しさや人間関係(ストレスフリー)、成長などです。

働く際には、給料で決めることが多いので、①②で入社してきます。
知り合いの社長が、「人は給料で決めて、人間関係で辞める」とよく言います。
特に最近は、非金銭の部分が大事で、「誰と働くかで決めたい」という学生も多いです。
人間関係や価値観が合わないと辛いですよね。
長期インターンでは、敢えて金銭報酬を低くしています。
これは、「金銭」と「非金銭」の総量を増やすためには、
非金銭的報酬を高めないといけなくするためです。
つまり、意義(誰を幸せにするか)や、マネジメント(自己成長のための研修やフィードバック、適切なコミュニケーション)などが整っていないと誰も参加しないし、やる気も続かない。
実際に、社長がなぜこのプロジェクトをやるかを社員が理解しておらず、
インターン生を通して理解してもらうことはよくあります。
社長は意義を言っているつもりでも、現場には伝わっていないのです。
また、マネジメントでは、中堅社員が若手への接し方の研修となることもあります。
しかもインターン生は、フルタイムでないことが多いので、多様な働き方の許容にも繋がります。
このように、社内で非金銭的報酬を高めるトレーニングができます。
もちろん①が最高です。
④に寄った状態から、①にあげていくことが重要だと考えています。
(そこは、プロジェクトで新事業を推進することとリンクします。)
”甲子園効果”で雰囲気を良くする
インターン生がやる気を出すと、それが周りへ伝わります。
これを私は”甲子園効果”と呼んでいます。
高校野球はプロほど上手くないけれど、一生懸命プレーする姿は感動と共感を起こします。
新しいことをやろうとすると、社員は「面倒くさいなぁ」とつい思ってしまうこともあるでしょう。
それが「インターン生が頑張っているから、手伝うか」となりやすいのです。
また、プロの中にアマが混ざっていて、良いプレーをされたら、プロは負けじと頑張りますよね。
社員もインターン生に負けないように、勉強したり、率先して行動したりという変化もみられます。
社内が一致団結し、前向きに働く雰囲気の良い会社にしていく効果があります。
選ぶから選ばれる会社へ
「将来はAIやロボットが普及し、ベーシックインカムになって働かなくてすむ」という話があります。
実際にそんな未来が来るかは分かりません。
しかし、ネットやロボットの進歩によって、仕事や働き方は多様化しているのは事実でしょう。
変化の激しい中、現状維持だけでは将来厳しい。
やりたくないことは効率化、代替していけば、やりたい仕事に集中できます。
「将来性があって、楽しく働ける。」
そんな会社なら働きたいと思う人がたくさんいると思います。
長期インターンは、人を連れてくることではなく、会社が変わることに価値がある。
つまり、働きたいと思える会社に変わることです。
時間はかかりますが、こうして採用力は向上していきます。
長期インターンを通して、学生を選ぶのではなく、選ばれる会社になりましょう!
